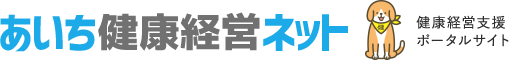トピー工業株式会社 豊川製造所
トピーコウギョウカブシキガイシャ トヨカワセイゾウショ
- 500~1000人
- 製造業/その他
| 所在地 | 〒442-8506 愛知県豊川市穂ノ原3-30 |
|---|---|
| URL | https://www.topy.co.jp/ja/index.html |
| 社員数 | 546名 |
| 業種 | 製造業/その他 |
- 業務内容
- 自動車用ホイール製造、自動車用プレス部品製造
健康経営に関する
自社のセールスポイント

当社は「健康なくして安全なし」を合言葉に、社員の健康保持・増進に本気で取り組んでいます。
健康診断後のフォローアップ、運動機会の促進、禁煙対策、メンタルヘルスケアを柱に、誰もが笑顔で働ける職場づくりを目指しています。
すべて開く閉じる
取組状況について
受診勧奨の取組
-
- 期間
- 2025年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- 当社では、従業員の健康保持・増進を目的として、定期健康診断および人間ドックを上期中に計画的に実施しています。
これは、健診結果の早期フィードバックと、必要な再検査を年度内に完了させることを目的とした取組です。
健診後には、年内を目途に全従業員へ結果を通知し、必要に応じて再検査や精密検査を促す案内を行っています。
対象者には、保健師や産業医が個別に対応するなど、受診の後押しを進めています。
今後も、従業員の健康リスクの早期把握と対応を通じて、誰もが安心して働ける環境づくりを進めてまいります。
-
- 取組に対する成果
- 当社では、本年度より新たに「受診勧奨の取組」を強化し、定期健康診断および人間ドックを上期中に計画的に完了させることで、健診結果の早期フィードバックと再検査の年度内完了を目指します。
健診後の再検査対象者に対しては、対象者を漏れなく把握し、保健師および管理職が連携して個別に声掛けを実施することで、確実な受診を促します。
この体制により、再検査の実施状況を可視化し、必要な支援や就業上の配慮につなげたいと考えています。
今後は、年度末に受診率や課題を分析し、さらなる改善活動につなげてまいります。
-
- 工夫したところ
- 本取組では、上期中に健診を完了するスケジュール設定に加え、保健師と管理職が連携して再検査対象者への声掛けを実施するなど、フォロー体制の強化を図ります。
また、対象者リストによる進捗管理や、受診しやすい環境づくりにも取り組み、確実な受診促進に向けた運用を進めてまいります。
管理職及び一般社員それぞれに対する教育
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- 管理職向け(ラインケア研修)
管理職を対象に、部下の健康管理・メンタルヘルス対策に関する知識と対応力の向上を目的とした「ラインケア研修」を実施。
メンタル不調の早期発見、職場環境改善、必要に応じた産業医・保健師との連携方法など、具体的な対応手順を学ぶ内容とした。
一般社員、管理職向け(セルフケア研修)
全社員を対象に、自身のストレス管理や生活習慣改善に関する知識を深める「セルフケア研修」を実施。
ストレス対処法、睡眠・運動・食事の基本、相談窓口の活用方法など、セルフマネジメント力の向上を目指す内容とした。
-
- 取組に対する成果
- ・ラインケア研修を受講した管理職から、「部下との面談や声掛けに自信が持てるようになった」などの声が寄せられた。
・セルフケア研修受講後、社員自身のストレス対策や健康行動への意識向上が見られた。
・研修後のアンケートでは、「早めに相談する意識が高まった」「ストレスとの向き合い方を学べた」といった肯定的な回答が多数あった。
・相談窓口(保健師面談等)の利用件数が増加し、早期対応につながるケースが増えた。
-
- 工夫したところ
- ①対象者ごとに研修テーマとアプローチを明確に分けた
・管理職には「部下対応力の向上」、一般社員には「自己管理力の向上」という役割に応じた教育設計を行った。
②実践的な研修内容を重視
・ラインケア研修ではロールプレイやケーススタディを取り入れ、即実践できるスキル習得に注力。
・セルフケア研修では、ワークや自己診断ツールを活用し、受講者自身が気づきと行動変容を促せる構成にした。
③受講ハードルを下げる工夫
・オンライン開催を導入し、拠点間格差なく誰もが受講できる環境を整備。
・研修時間もコンパクトに設定し、業務負担を最小限に配慮した。
・事後フォロー体制の整備
・研修後にフォローアップ資料や相談窓口情報を提供し、学びを実践につなげやすい仕組みを作った。
禁煙対策
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①敷地内全面禁煙の実施
・健康増進法および受動喫煙防止対策の強化を受け、当社では敷地内(建物内外すべて)を全面禁煙としました。
②就業時間内全面禁煙の導入
・労働時間中の喫煙を禁止し、勤務中は禁煙を徹底する方針を打ち出しました。
③全社員向けの事前説明と周知活動
・実施前には、全社員に向けた説明会・周知文書の配布を実施し、方針の趣旨と意義について理解を促しました。
④段階的な施行
・いきなり全面施行するのではなく、一定の猶予期間を設けて周知徹底を図り、混乱を最小限に抑える運用を行いました。
-
- 取組に対する成果
- ①敷地内および就業時間内の喫煙は大幅に減少
・敷地内や就業時間中の喫煙に関する違反報告は、施行後ほぼ発生していない状況。
②職場環境の美化や受動喫煙リスクの低減
・敷地内のたばこのポイ捨てが解消され、清潔な環境維持に寄与。
③健康意識の向上への波及効果
・禁煙をきっかけに、健康意識が高まった社員が増加。
・社員向け健康施策(ウォーキングイベント、生活習慣病予防活動など)への参加率にも良い影響が出始めている。
-
- 工夫したところ
- ①事前説明を重ねて実施への理解を促進
・禁煙方針に対して強い反発もあったため、社員説明会を複数回開催し、経緯・目的・メリットを丁寧に伝えた。
②トップメッセージの発信
・全社的な方針として統一感を持たせるため、経営層からの明確な禁煙推進メッセージを発信した。
③移行期間を設け、混乱を防止
・施行日までに一定の移行期間を設定し、社員が心の準備を整えられるよう配慮した。
④禁煙支援策の整備
・希望者には、禁煙外来の紹介や禁煙補助グッズ情報の提供など、個別支援も準備し、無理なく取り組める環境づくりに努めた。
健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
-
- 期間
- 2024年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①健康増進に向けた目標設定と推進
・定期健康診断の受診率100%を目指し、上期中に受診を完了させ、年内にフィードバックを実施。
・再検査対象者に対する受診促進を強化し、年度内受診率90%以上を目標とした。
・セルフケア研修の受講率90%以上を目標に、全社員への自己管理教育を推進。
・敷地内および就業時間内全面禁煙を実施し、職場環境の美化と健康リスク低減を図った。
②過重労働防止に向けた目標設定と管理
・月45時間超の時間外労働者ゼロを中期目標とし、長時間労働者(月80時間超)に対する産業医面談を100%実施。
・年次有給休暇の取得率70%以上を目指し、休暇取得促進の呼びかけを行った。
-
- 取組に対する成果
- ・健康診断受診率は全社で100%を達成。
・健診結果のフィードバックを年内に完了し、再検査対象者への個別声掛け体制が定着。
・セルフケア研修は高い受講率を記録し、受講者からは「ストレス対処への意識が高まった」などの声が寄せられた。
・敷地内・就業時間内の喫煙行為は大幅に減少し、職場環境の美化にもつながった。
・有給休暇取得率も前年より向上傾向にあり、働き方改革の推進に寄与している。
-
- 工夫したところ
- ・数値目標を明確に掲げ、進捗を「見える化」
→ 健診受診率、再検査受診率、残業時間、有給取得率などを定期的に集計・共有し、意識づけを強化。
・健康施策と労働時間管理を一体で推進
→ 健康づくりだけでなく、働き方の改善(残業抑制・休暇取得促進)も同時に取り組み、相乗効果を狙った。
・早期対応を可能とするスケジュール設定
→ 健診実施時期や面談実施時期を前倒しすることで、年度内の確実な対応を可能とした。
・現場負担への配慮を重視
→ 研修や施策はできるだけ業務への影響を抑え、受講しやすい環境・取り組みやすい仕組みづくりに努めた。
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・定期健康診断後の結果分析において、産業医・保健師が参加し、健康リスクの傾向を把握。
・受診勧奨、再検査フォロー、重症化予防施策(特定保健指導案内など)について、産業医・保健師が主体的に助言・提案。
・禁煙対策(敷地内全面禁煙・就業時間内禁煙)の施策決定にも、産業医・保健師がリスク評価と方針提案を行った。
・健康教育(セルフケア研修)の内容検討においても、産業医・保健師の意見を反映し、実務に即したテーマ設定を行った。
-
- 取組に対する成果
- ・産業医・保健師がかかわることで、施策が現場の健康課題に即した実効性あるものとなった。
・健康診断後の再検査フォローが強化され、年度内受診率向上に寄与した。
・敷地内禁煙施策に対して、産業医・保健師から科学的根拠に基づく説明があったため、従業員の理解が進んだ。
・セルフケア研修受講後、社員の健康意識向上やストレス対処行動の変化がみられるなど、効果が表れ始めている。
-
- 工夫したところ
- ①データに基づく立案を重視
・健診結果や産業医意見書など、客観データをもとに議論・施策立案を行い、取り組みの説得力を高めた。
②産業医・保健師との定期的な打ち合わせを設定
・月1回の健康管理部門ミーティングに産業医・保健師が参加し、課題共有と改善策検討を継続的に実施。
③わかりやすい情報発信を推進
・禁煙対策や健康教育の際には、産業医・保健師監修のもと、従業員向けにわかりやすく資料を作成し、現場の納得感を得る工夫をした。
適切な働き方の実現
-
- 期間
- 2022年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①長時間労働の抑制
・月40時間超の時間外労働ゼロを目標に掲げ、各部門において業務量・業務内容の適正化を推進。
・月60時間超の時間外労働者に対しては、産業医面談を100%実施し、健康リスク管理を徹底。
②年次有給休暇の取得促進
・年次有給休暇取得率70%以上を目標に設定し、計画的な休暇取得を奨励。
③柔軟な働き方の導入
・職種に応じた在宅勤務や時差出勤の活用も推進し、多様な働き方を支援。
-
- 取組に対する成果
- ・月40時間超の時間外労働者は、前年に比べ減少傾向。
・月60時間超の長時間労働者への産業医面談実施率は100%を達成。
・年次有給休暇の取得率が、前年度より数ポイント向上し、計画的取得が進みつつある。
・柔軟な働き方の推進により、従業員満足度の向上や定着率の改善にも良い影響が出始めている。
-
- 工夫したところ
- ①数値目標の明確化と見える化
・残業時間、有給休暇取得率などを定期的に集計し、管理職へフィードバックを実施。
②上司向けマネジメント支援
・管理職向けに「ラインケア研修」を開催し、適切な労働時間管理の意識向上を図った。
③休みやすい風土づくり
・有給取得推進週間を設けるとともに、上司自身が率先して休暇取得を行うことで、部下も休みやすい環境をつくった。
④健康と働き方をセットで捉える施策
単なる労働時間管理にとどまらず、健康管理(健診結果・ストレスチェック結果)と働き方を連動させたフォローを行った。
コミュニケーションの促進
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①管理職と部下との対話強化(ラインケア研修)
・管理職を対象に、部下との面談や声掛けスキル向上を目的とした「ラインケア研修」を実施し、対話を通じた健康管理意識の向上を図った。
②従業員自身の相談行動促進(セルフケア研修)
・一般社員向けに「セルフケア研修」を実施し、困ったときには一人で抱え込まず相談する大切さを啓発。
③全社共通イベントの開催
ウォーキングイベント(歩こうフェス)等、全社員が参加できる健康増進イベントを実施し、部署を越えた交流の機会を創出した。
-
- 取組に対する成果
- ①ラインケア研修後、「部下と健康や働き方について話す機会が増えた」と回答した管理職が増加。
②セルフケア研修後、相談窓口(産業医・保健師・人事)への問い合わせ件数が増加し、早期対応事例が増えた。
③再検査勧奨において、保健師・管理職からの個別声掛けが自然な対話のきっかけとなり、受診率向上にも寄与。
④健康イベントでは、部署間交流により従業員同士のつながりや一体感が向上した。
-
- 工夫したところ
- ①研修を対話スキルに直結する設計にした
・ラインケア研修では、単なる知識習得だけでなく、実際に声掛けや面談をロールプレイで体験できる内容とした。
②社員自身が“相談してよい”と思える雰囲気づくり
・セルフケア研修では、相談行動をポジティブに捉えるメッセージを強調し、心理的ハードルを下げた。
③健康施策に「声掛け」の機会を組み込んだ
・受診勧奨やイベント案内時に、単なる連絡にとどまらず、顔を合わせて話すきっかけを意識的に設定した。
④部署を越えた交流促進
・健康イベントでは、チーム制やポイント制を導入し、自然なコミュニケーションを生み出す仕掛けを施した。
治療と仕事の両立支援
-
- 期間
- 2022年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①産業医・保健師による両立支援面談の実施
・治療が必要な従業員に対して、産業医・保健師による面談を実施し、働き方や勤務上の配慮事項について支援。
②就業上の配慮措置の整備
・通院時間の確保(時間帯年休制度)、勤務時間短縮、在宅勤務など、治療と仕事の両立を支援する勤務措置を整備。
③人事・産業保健スタッフ・現場上司の連携強化
・両立支援がスムーズに行われるよう、本人同意のもとで関係者間の情報共有体制を整備。
④相談窓口の明確化と周知
・両立支援に関する相談窓口(人事・保健師)を社内イントラ等で周知し、安心して相談できる体制を構築。
-
- 取組に対する成果
- ・体調不良者や通院中の従業員に対して、柔軟な勤務対応が実施されるケースが増加。
・産業医・保健師面談を経て、就業上の配慮を受けながら継続就業している従業員が複数名いる。
・従業員からも、「治療しながら働く選択肢があることに安心した」という声が寄せられている。
・離職防止にも寄与し、従業員定着率の改善傾向が見られている。
-
- 工夫したところ
- ①本人のプライバシー保護を最優先
・治療内容や病名などセンシティブな情報については、本人の同意を得た範囲のみ共有し、安心して支援を受けられる体制とした。
②個別対応の柔軟性を重視
・病状や治療スケジュールに応じ、画一的な対応ではなく個別に最適な支援策を検討・提案。
③早期相談を促す取組
・セルフケア研修や社内広報を通じて、「体調に不安があれば早めに相談」する文化づくりを進めた。
④上司への啓発
ラインケア研修内で、「治療と仕事の両立支援における管理職の役割」も伝え、現場対応力の向上を図った。
保健指導の実施
-
- 期間
- 2022年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①健康診断後の保健指導
・健康診断結果において、再検査・要精密検査・生活習慣改善が必要と判定された社員に対して、保健師が個別に保健指導を実施。
・健診結果説明、生活習慣改善のアドバイス、受診促進、フォローアップを一体的に行った。
②特定保健指導の案内と支援
・40歳以上の社員を対象に、特定健診結果に基づく特定保健指導を実施。対象者には積極的に参加を案内。
③高リスク者への重点対応
・血圧・血糖・脂質異常等、リスクの高い項目に該当した社員については、保健師および産業医が連携し、重点的に支援。
④セルフケア啓発活動
・生活習慣病予防をテーマとしたセルフケア研修や健康情報の配信を実施し、社員自身が健康管理できる力を育成。
-
- 取組に対する成果
- ・再検査・要精密検査対象者への保健指導実施率が向上し、年度内受診率向上に寄与。
・保健師による面談後、生活習慣改善(例:減量・禁煙・運動習慣)に成功した事例が複数確認されている。
・特定保健指導への参加率も徐々に上昇傾向にあり、重症化予防活動が定着しつつある。
・健康意識が高まったことで、健康イベント(ウォーキングなど)への参加者数も増加した。
-
- 工夫したところ
- ①個別アプローチによる動機づけ
・健診結果だけにとどまらず、本人の生活背景や価値観に配慮した保健指導を行い、納得感のある支援を重視。
②保健師・産業医の連携強化
・ハイリスク者に対しては、保健師と産業医が情報を共有し、医療的視点と行動変容支援の両面からサポートを実施。
③スモールステップで行動変容支援
大きな目標を一度に求めず、小さな行動改善から始める支援方法を取り入れ、成功体験を積み上げる工夫を行った。
④継続フォロー体制の整備
・面談後に1回限りで終わらず、メールや面談による継続フォローを実施し、行動定着を支援した。
食生活の改善
-
- 期間
- 2024年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①健康教育(セルフケア研修)での食生活テーマ設定
・セルフケア研修において、「バランスの良い食事」「減塩・適量」など食習慣改善をテーマに取り上げ、社員の理解を促進。
②健康情報の定期配信
・社内ポータルやイントラネットを通じて、食生活改善に関するコラムやワンポイントアドバイスを定期配信。
③生活習慣病リスク者への個別保健指導
・健診結果で血圧・血糖・脂質異常のリスクが認められた社員に対して、保健師が個別に食事内容を含めた生活改善指導を実施。
④健康イベントと連動した啓発活動
・ウォーキングイベント(歩こうフェス)期間中に、食事と運動の両面から健康づくりを啓発する取り組みも併せて実施。
-
- 取組に対する成果
- ・セルフケア研修後、「食事内容を見直すきっかけになった」という受講者の声が多数寄せられた。
・個別保健指導を受けた社員の中から、体重減少や血糖値・血圧改善につながった事例が複数確認されている。
・健康情報配信後の社内アンケートでは、「意識して野菜を摂るようになった」「間食を控えるようになった」と回答する社員が増加。
・全社的な健康意識向上により、食生活改善を意識した健康行動が広がりつつある。
-
- 工夫したところ
- ①難しい話ではなく「実践できるコツ」を中心に発信
・「減らす」「制限する」だけでなく、「できることをプラスする」ポジティブなアプローチで情報提供。
②短期間で完結する啓発テーマ
・長期的な話だけではなく、「まず1週間だけ減塩チャレンジ」など小さな目標設定で実践しやすくした。
③運動施策と組み合わせて効果を訴求
・食事改善だけを押し付けず、運動施策(ウォーキングイベント)と連動して相乗効果を図る工夫を行った。
④個別指導では「無理をさせない」
・個別保健指導では、本人のライフスタイルを尊重し、取り組みやすい小さな改善から支援した。
運動機会の促進
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①ウォーキングイベント(歩こうフェス)の実施
・全社員を対象としたウォーキングイベントを開催し、歩数目標達成を目指すチャレンジ企画を実施。
・部署単位・チーム単位での参加も可能とし、仲間と取り組める仕掛けを用意。
②運動啓発の実施(セルフケア研修内)
・セルフケア研修において、運動の重要性や簡単にできる運動習慣(例:スロースクワット、ストレッチ)の紹介を実施。
③社内向け健康情報の発信
・社内ポータルを通じて、短時間でできる運動のコツを定期的に発信。
-
- 取組に対する成果
- ①ウォーキングイベント参加者の約6割が、期間中に1日平均8,000歩以上を達成。
②イベント後のアンケートでは、「運動習慣を意識するきっかけになった」と回答した社員が多数。
③セルフケア研修後、「家でもできる簡単な運動を始めた」という報告が増加。
④日常的な活動量向上への意識が高まり、エレベーター利用控えの行動変容が見られた。
-
- 工夫したところ
- ①「楽しさ」と「達成感」を重視したイベント設計
・ウォーキングイベントでは、単なる個人記録ではなく、チーム対抗形式や達成報酬を設定してモチベーションを高めた。
②「できることから始める」啓発アプローチ
・セルフケア研修や社内配信では、運動が苦手な人でも始めやすい内容(無理のないストレッチや短時間運動)を重視。
③普段の生活に自然に組み込む工夫
・通勤・社内移動時の徒歩推奨など、日常動作の中で運動量を増やす提案を行い、ハードルを下げた。
④参加しやすい環境づくり
・イベント参加を任意としつつ、部署単位での参加推進を促すことで、「みんなでやる」雰囲気を醸成した。
従業員の感染症予防
-
- 期間
- 2020年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①感染症対策ガイドラインの策定と周知
・インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症対策として、社内ガイドラインを策定し、従業員へ周知。
②感染症予防教育の実施
・セルフケア研修や社内配信を通じて、手洗い・咳エチケット・換気・マスク着用など基本的な感染予防行動の徹底を啓発。
③ワクチン接種の推奨・支援
・インフルエンザワクチン接種を推奨し、希望者に対する会社補助制度の導入や接種機会の案内を実施。
④職場環境の整備
・事務所・休憩室・食堂等に、アルコール消毒液・マスク・体温計の設置。
・密を避けるため、座席配置の工夫やリモート会議の活用も推進。
⑤体調不良時の早期対応
・発熱・風邪症状が見られた場合には、無理に出勤せず、早期に医療機関受診・自宅療養を促す運用を徹底。
-
- 取組に対する成果
- ①社内でのインフルエンザ・新型コロナウイルス感染拡大を最小限に抑えることができた。
②従業員の感染症予防行動(手洗い・マスク着用など)が日常習慣として定着。
③インフルエンザワクチン接種率が前年比で向上。
④感染症流行時でも、業務継続性を維持できた(大規模なクラスター発生なし)。
-
- 工夫したところ
- ①正しい情報を迅速かつわかりやすく伝達
・社内ポータルや掲示物を活用し、タイムリーで信頼性の高い情報発信を重視。
②予防行動を“押しつけない”工夫
・感染症予防を義務ではなく、「自分と周囲を守る行動」として前向きに促す表現に配慮。
③心理的な不安にも対応
・不安を抱える従業員に対して、保健師が相談対応を実施し、安心して働けるサポート体制を整えた。
④現場の声を取り入れた改善
・感染症対策に関して、現場アンケートや意見箱を設置し、必要に応じて運用の見直しや物品の追加を実施。
長時間労働への対策
-
- 期間
- 2020年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①時間外労働の上限管理の徹底
・月40時間超の時間外労働ゼロを目標に設定し、各部門単位で時間外労働の状況をモニタリング。
・超過が見込まれる場合は、早期に対応策(業務調整・増員検討等)を指導。
②長時間労働者への産業医面談の実施
・月60時間超の時間外労働者に対して、産業医面談を100%実施し、健康状態確認と就業上の助言を行った。
③長時間労働防止のための管理職教育
・ラインケア研修や労務管理研修において、労働時間管理の重要性や健康リスクについて啓発。
④年次有給休暇取得促進
・有給休暇取得を推進し、業務過多による長時間労働の慢性化防止に取り組んだ。
-
- 取組に対する成果
- ・月40時間超の時間外労働者数が前年より減少傾向。
・月60時間超の労働者に対する産業医面談実施率100%を継続。
・長時間労働に起因する健康障害リスク(過労死ライン超えリスク)が低下傾向。
・有給休暇取得率も向上し、適正な業務配分意識が浸透し始めている。
-
- 工夫したところ
- ①早期のリスク検知と対応
・月次で時間外労働データをチェックし、基準超過が見込まれる段階で早期警告・改善指導を行った。
②健康面からのアプローチ
・単なる労働時間規制ではなく、健康リスク(脳・心疾患・メンタル不調)の啓発を通じて自主的な行動変容を促進。
③業務見直し支援
・長時間労働者に対して、本人・上司・人事担当で業務棚卸しと負荷軽減策を検討する仕組みを導入。
④「休み方改革」の推進
・有給休暇の「まとめ取り」や「分散取得」を奨励し、休みやすい風土づくりにも注力した。
メンタルヘルス不調者への対応
-
- 期間
- 2020年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①ラインケア研修の実施
・管理職を対象に、部下のメンタル不調の早期発見・対応方法を学ぶラインケア研修を実施し、現場対応力を強化。
②セルフケア研修の実施
・全社員向けに、ストレスマネジメントや相談行動の促進を目的としたセルフケア研修を実施。
③ストレスチェックの活用
・毎年実施するストレスチェックの結果をもとに、高ストレス者に対する面談勧奨と職場環境改善を推進。
④保健師・産業医による相談体制の整備
・保健師や産業医による相談窓口を常設し、不調の兆しがある社員への早期介入・支援を行う体制を整備。
⑤職場復帰支援プログラムの整備
・休職者の職場復帰にあたっては、段階的な復帰支援(短時間勤務・業務配慮など)を行い、無理のない復帰を支援。
-
- 取組に対する成果
- ・ラインケア研修後、「部下の変化に早めに気づく意識が高まった」という管理職の声が増加。
・セルフケア研修後、相談窓口の利用件数が増加し、早期対応につながったケースが見られる。
・ストレスチェック高ストレス者への面談勧奨率が向上し、早期の対応・フォローアップ体制が定着。
・メンタル不調による長期休職者の復帰率が向上し、復帰後の定着支援も順調に進んでいる。
-
- 工夫したところ
- ①現場で「気づきやすい」教育
・ラインケア研修では、不調の兆し(遅刻・欠勤、業務ミス、表情の変化など)に気づく視点を具体的に伝授。
②社員が「相談しやすい」環境づくり
・セルフケア研修や社内掲示を通じ、相談行動は恥ずかしいことではない、早めの相談が大切というメッセージを強調。
③ストレスチェック結果を「活用する」文化づくり
・ストレスチェックを単なる数値確認で終わらせず、産業医・人事・職場でのフォローに具体的につなげる運用を行った。
④職場復帰後もきめ細かなサポート
・復帰後も保健師・上司による定期フォロー面談を実施し、再発防止に向けた継続支援体制を整備。
女性の健康保持・増進に向けた取組
-
- 期間
- 2022年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①婦人科検診の受診促進
・子宮頸がん検診・乳がん検診について、会社から案内を行い、定期的な受診を推奨。
・対象者には健診オプション案内や自己負担軽減支援を実施。
②女性特有の健康課題に関する啓発
・管理職研修において、更年期症状、月経困難症、妊娠・出産に伴う体調変化への理解を促進。
③相談体制の整備
・保健師による女性向け健康相談窓口を設置し、健康課題に関する気軽な相談機会を提供。
④休暇・勤務制度の活用支援
・体調に応じた特別休暇(生理休暇)や短時間勤務制度の周知と、利用しやすい環境整備を推進。
-
- 取組に対する成果
- ①婦人科検診の受診率が前年より向上し、健康リスクの早期発見・対応につながっている。
②管理職研修後、「女性特有の体調変化に対する理解が深まった」との受講者アンケート結果が得られた。
③保健師相談窓口の利用が進み、早期相談・受診勧奨につながるケースが増加。
④女性従業員から、「体調に配慮しながら働ける職場だと感じる」という声が挙がり、定着率向上にも寄与している。
-
- 工夫したところ
- ①対象者への積極的な声掛け・案内
・婦人科検診や相談窓口について、対象者へ個別メールや掲示で丁寧に案内し、受診・相談への心理的ハードルを下げた。
②ライフステージごとの支援を意識
・妊娠・出産・更年期など、ライフステージに応じた課題に配慮した情報提供と支援を展開。
③プライバシーに配慮した相談対応
・相談内容については、本人のプライバシーを最優先し、安心して相談できる体制を整備。
④男女ともに理解を深める啓発
・女性社員だけでなく、管理職や男性社員にも女性特有の健康課題を啓発し、職場全体で支え合う風土づくりを進めた。